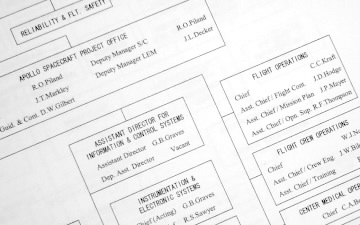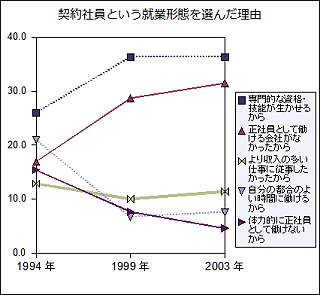“ぶっとび宇宙飛行士”の軽快な自伝。企業経営の立場からは、NASA組織の問題点についての生々しい描写が特に気になります。宇宙飛行士を目指す方にとっては、宇宙飛行士という仕事の実像について触れられる良い材料だと思われます。

「ライディング・ロケット」(上下巻 概観)
【マイク・ミュレイン(著)、金子浩(訳)、2008年刊(原著は2006年刊)、化学同人】
■下ネタ満載、本音も満載
この2月にJAXA(宇宙航空研究開発機構)が10年ぶりの宇宙飛行士選抜を発表して以来、当サイトに「宇宙飛行士」をキーワードにしてアクセスされる方が増えました。特に宇宙飛行士の選抜について書いた記事「中年ドクター 宇宙飛行士受験奮戦記」をご覧になる方がどっと増えたのがここ数カ月の特徴です。その選抜時(10年前)の合格者である星出飛行士が乗り込むスペースシャトルSTS-124ミッションは、打ち上げがまもなくに迫っています。
本書「ライディング・ロケット」は、“著名な宇宙飛行士が書いた真面目な記録”というものからは程遠いユニークな本です。一言で言うと、下ネタ満載のとんでもない本(笑)。たとえば「コンドーム」という言葉が一体何回出てくるか、女性差別的発言が何回出てくるか…。さらには、宇宙空間でエイリアンと会って合体したとかいう冗談まで言い出す始末。真面目な記録の中にこうした下ネタが1つでもあると問題視されそうですが、上下巻で600ページ超(日本語訳版)、全42章にわたる長編の半分をこうした下ネタで確信犯的に埋め尽くしていれば、もうそこには違和感など持ちようがないのが面白いところです。
“ぶっとび”の理由は、物語の半分を占める下ネタばかりではありません。残りの半分には、下ネタと同じ軽いノリで書かれていながら、内容的にはNASAという組織内部の特定の人たちに向けた「辛辣な批判」が満載されています。しかし、辛辣な批判の数々も笑いの種と一緒くたになって語られていることが、これまた妙に悪い気分を読者に感じさせません。実にうまい味付けになっています。
■秘密主義が組織・メンバーの士気を損なう
1970年代から80年代にかけて、ジョンソン宇宙センターで絶大な権力を振るっていたジョージ・アビーという人物がいました(当時「搭乗員運用管理局長」)。この人については、宇宙ステーション・ミールを舞台にしたノンフィクション「ドラゴンフライ」でかなり辛辣に描写されていて、そのことを本サイトでも採り上げました(参考:「ドラゴンフライ」3-官僚組織化する宇宙機関)。しかしアビーを糾弾する度合いにかけては、本書の方がさらにスゴイ。著者ミュレインたちがアビーの命令の下で辛い思いをしていたときの、悲鳴のようなものが聞こえます。宇宙飛行士たちにとってNASAに棲息する元凶のような存在だったと…。
かいつまんで言うと、
・アビーは宇宙飛行士たちのミッションへの割り当てに関する権限を一人で持つなど、専制的に振る舞い、そのために多くの宇宙飛行士がアビーを蛇蝎のように嫌っていた
・アビーは自分がコントロールできないコミュニケーション・ルートが組織内に生まれることを極度に嫌い、結果として組織内に疑心暗鬼を生んだ
・アビーは飛行士割り当てのルールをほとんど示さず徹底した秘密主義をとり、その結果として宇宙飛行士の士気を損なっていった
などです。
著者については、宇宙飛行士になってから相当に長い間待たされた挙句、アビーからやっと初フライトの割り当てが言い渡されました。それはスペースシャトルの新しい機体ディスカバリー号の初フライトでした。そのときのことを、こんな風に表現しています。
「私たちは(アビーから)ディスカバリーの初飛行をまかせられた。ストックホルム症候群の人質のごとく、私たちは皆、平身低頭して(アビー)に感謝した」。
■問題解決の必要性がわかっていても、手をつけられない
こうした事例は、現代の企業組織でもときどき発生しているモデルとも言えるでしょう。
→トップが何らかの面(営業的な実績があるなど)で優秀な場合、権限を最大限発揮し、できる限り組織を自分の管理下で動かそうとしがちになります。
→多くの場合、組織内の横のコミュニケーションを(口ではともかく本心では)あまり好みません。
→これが組織に浸透してくると、トップ下の管理職までもがそれぞれ主導権を取り合い、権力のせめぎ合いが起こりがちになります。
→権力者に擦り寄り、おべんちゃらを言うメンバーが増える一方、互いに裏では悪口ばかり言う、ひねくれた組織風土ができてきます。
→仕事に対しても、本来の目的や効果より社内力学や諦めが前面に出てきて官僚化が進みます。
そんな事例は、いろいろな会社に関わっていると何度となく実際に目にされるものです。
本書および「ドラゴンフライ」のアビー評/NASA評はほぼ一致しています。つまりこの時代のNASA(少なくともジョンソン宇宙センターなどスペースシャトルのプロジェクトを企画・運営する組織)は、アビーの専制的管理体制の下、そんな危険な組織風土を持っていたことが確かなようです。きちんと問題点がしかるべきところに伝わらない、もしくは問題解決の必要性がわかっていても誰も手をつけられない…。本書からは、宇宙飛行士たちのそんなもどかしさと危機感が読み取れます。
そんな体制が1986年のチャレンジャー号事故と2003年のコロンビア号事故につながったことを、著者は、軽めのノリの文章でオブラートに包みながらも、“当事者として”説得力ある説明をしています。なにしろ、宇宙飛行士の割り当てが少し違っていただけで、著者自身が事故を起こしたチャレンジャーに乗り組んでいた可能性があったのです。現実は、著者の特に親しい同僚のうち何人かがこのチャレンジャー事故で亡くなっているのを目前に見ています。
さらに、チャレンジャー事故後再開されて間もなく著者が乗り組んだSTS-27ミッションでは、打ち上げ時に(後の)コロンビア事故と似たような損傷を受けていて、帰還時に700枚の耐熱パネルが剥がれていました。それを帰還前にクルーも地上も認識していたにも関わらず、“賭け”のようにして帰還(大気圏突入)を命令された経験がありました。後から考えると、このときコロンビア号のように空中分解せずにすんだのは、まさに幸運に助けられた結果だった模様です。
■優秀な人も、役職次第で害となる
アビーと並んでもう一人、著者を悩ましたとされるのが、アポロ時代のムーンウォーカーの一人ジョン・ヤングとのこと。ヤングは、ジェミニの時代から宇宙飛行の経験を積み、(失敗して命を失う危険がかなりあったとされる)スペースシャトルの初フライトにも船長として乗り組んだ、いわば全世界で最も経験を積んだ宇宙飛行士とも言える人です。本書が書かれたこの時期のヤングは「宇宙飛行士室長」で、現場を取りまとめる最高責任者のような役割を持っていたはずでした。
ヤングについては、「月の記憶」という本の中で、心をなかなか開かない気難しい男性であるような描写がありました(参考:「月の記憶 アポロ宇宙飛行士たちの『その後』」。「月の記憶」を読んだときはどうも腑に落ちないヤング評でしたが、本書を読むとさらに意固地な性格があったことがわかります。
ヤングの直接の命令で動いていた著者が、あまりのヤングの聴く耳の持たなさに閉口させられ、たびたびヤングの激怒の対象となり、敵視され、精神的に追い詰められてしまう…。本書にはそんな経緯がけっこう細かく描かれています。挙句、著者は理不尽なプレッシャーにより精神的にダメージを受け、意を決して精神科の医師を訪れるに至ります。
「ヤングとアビーのせいで頭がおかしくなりそうなんです」。
そこで精神科の医師からは、こんな言葉が返ってきました。
「同僚の宇宙飛行士のみなさんから(同じような話を)うかがってますよ」!
著者をはじめ宇宙飛行士の誰もが、ヤングの“宇宙船を操る技量や勇気”を高く評価してはいたのは事実のようです。しかし、管理職という役職としてのヤングの力量はかなり弱かったことがうかがえます。いくら優秀な人も、その人に合わない役職につけられると、本人も周囲も不幸になるという典型のようです。その他、組織やリーダーシップについて考えさせられるケースがいくつか紹介されていますので、興味のある方はぜひ本書を読んでみてください。
いずれヤングもアビーもそれぞれの役職を去ることになるのですが、それを惜しむものなどいないどころか、皆揃って祝杯をあげるほど喜んだそうです。アビーの送別パーティーが行われたときは、本人を前にしながら、暴君的振る舞いに対する痛烈な批判と皮肉が浴びせかけられるほどだったとのことです。
■宇宙飛行士としての条件?
それにしても、宇宙飛行士という仕事の先の見えなさ、NASA上層部に対する疑念…。
一方で、ほんの数回しか実経験できなくても、命を賭けた宇宙飛行ミッションという仕事の素晴らしさ…。
そのバランスの中で、著者のマイク・ミュレインは、時に危うい精神状態を保ちながら、時に許される範囲で精一杯の悪ふざけを興じながら、全体的には前向きの人生を送ってきたようです。
著者は、自分を含め、女性に対して失礼なことばかりする粗野なパイロット仲間たち全員を「惑星AD(Arrested Development:発育不全)出身」と表現しています。宇宙飛行士とはいえ人格者とはかけ離れたような存在と自覚しているようです。特に自分のことは「本当は落第生なのに間違って宇宙飛行士に選ばれてしまったに違いない」といった表現をするほどです。その前提の下で、下ネタを飛ばし、毒舌を飛ばし、自虐的ギャグを飛ばし、でも誇りを失わず、真正面から宇宙飛行士の実像を描いた本書は魅力的です。
しかもこれだけの下ネタも下品にならず、これだけの批判的意見にも悪意が感じられないのは、おそらく著者の人柄によるのでしょう。また、あけすけに表現しているにも関わらず、書かれていることはおそらくすべて公表して問題ないものと判断していることをうかがわせます(たとえばミュレインが飛んだ3回のミッションのうち2回は軍事機密に関わる任務についていたため、シャトルでの仕事内容はまったくといってよいほど語られていません)。さらに、自分が宇宙に行けたのは「NASAのチームの肩に乗せてもらったから」であり、数え切れないほどの人々に「心からの尊敬と称讃の念」を抱いていることも口にしています。
下品になる一歩手前、ブラックになる一歩手前まで突っ込んでも度を越えない絶妙のバランス感覚をみると、やはりこの人も宇宙飛行士としてのライト・スタッフ=正しい資質を持った人なのだろうと推測されます。だからこそ(自らの自虐的表現とは裏腹に)宇宙飛行士選抜のプロセスを通過したこと、そして3度もの宇宙ミッションに参加できたのだろうことを納得させられます。たんに“ぶっとんだ”だけの人物、シニカルなだけ人物では、万が一“間違って選ばれた”のが事実としても重要な任務に複数回つけるものではありません。相当の覚悟とプロ意識、さらには意に沿わぬ上司や組織の命令とも折り合いをつけてやっていくだけの見識を持っていることが、宇宙飛行士として選ばれるために必要な条件だったに違いありません。
■宇宙飛行士になるという、じつに特殊な覚悟
本書の記述からは、宇宙飛行士の間には、自分たちと同様に厳しい訓練をし、難しい仕事をしてきた仲間であれば、それが女性であろうが研究者出身であろうがどんな国籍であろうが差別せず、同じ仲間として認める意識が確実にあることがみてとれます。一方そうでない人、いわゆる“お客さん飛行士”(世間の注目を得たりスポンサーを満足させたりするために、主に政治的な思惑から搭乗させるパートタイム宇宙飛行士。宇宙に理解を示している顔して同乗を画策する政治家や有名人や一部のペイロード・スペシャリスト)に対しては、「我々が宇宙に行く機会を奪っている奴等」として反感を持つと、本書の中に何度か描かれています。
そのうちの一つにSTS-95ミッションで77歳のジョン・グレン(マーキュリー計画「オリジナル7」の一人、米国3人目の宇宙飛行士、後に上院議員)が飛ぶことになったことにも触れられています。曰く、「(グレンは)ミッションに不可欠ではない人物。老年医学研究うんぬんはたわごと。例によって有力な政治家のための口実。グレンの個人的満足のためリクスを犯すなど正気の沙汰ではなかった…」と。
こうしたドロドロした話を読むと、“お客さん宇宙飛行士”が周囲から受けたであろう冷たい視線が推測できます。また、当初はペイロード・スペシャリストであった毛利さんが後にミッション・スペシャリストとして厳しい訓練をして再挑戦したことの意味も、その後の土井さん、若田さん、野口さんが苦労して宇宙飛行士仲間の信頼を築いていったことの価値も、(あくまでも連想にすぎませんが)本書から間接的に感じることができるかもしれません。
これから1年近くかけて行われるJAXAの宇宙飛行士試験を目指す方々には、それだけの覚悟と責任感と、そして仮に宇宙飛行士に選ばれたとしても何もできず無為に人生が終わる可能性があるという覚悟さえも求められることでしょう。でも…………、
そんな覚悟を持つ方がたくさん発掘されることもまた、社会から期待されていることでしょう。