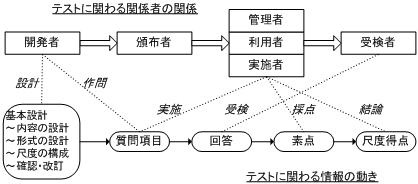個人の頭の中に閉じ込められている技を他人に伝えたり、言葉にしにくいものをなんとか言葉にしていく…。脳科学を応用してそのプロセスをスマートに進めることはできないものでしょうか。
(今回の記事は、個人的な観測ばかり含めた内容です。紹介している本と記事の内容に強いつながりがあるとは言えませんので、その点ご容赦を)

〔日本語は論理的である、脳科学からの第二言語習得論〕
■個人を対象にした脳科学の応用
脳科学の社会への応用が進んでいることを「身体を測る 11-脳の非侵襲的測定」と「脳測定とマーケティング」で触れました。ニューロ・マーケティングやニューロ・エコノミクスは普通、多数の人や組織を対象にして、社会の中で戦略・戦術を考える場面で応用されます。
一方、個人を対象とした分野にも脳科学はもちろん応用でき、“脳トレ”がその応用例にあたります。ただし、一足飛びに結果を求める脳トレにまがい物があふれていることは否定しようがありません。現実の科学ではもっと地味な研究が一歩一歩進められているところでしょう。本サイトのテーマからすると、例えば
(1) 個人のより客観的な心理アセスメント
(2) 技能技術の伝承や、暗黙知の形式知化
につながるきっかけを脳科学に期待したいところです。
■技の伝承をスムーズに進めたい
上記2つのテーマのうち(2)、つまり個人がどのように特定の技能を習得していけばよいか、あるいは言葉で伝えにくい技を人に伝承させていけばよいかについて、最近発表されてくる脳科学研究を役に立てることはできないものでしょうか。“ニューロ・ワーディング”(neuro-wording)とでも名付けましょう(つい今しがた、この原稿を書いている間にひねり出した完全な造語です)。
これは一つの問題意識を示しただけで、その確固たる手がかりが私(松山)にあるわけではありません。実際の企業内での人材育成、技術伝承の手法を考えるときには、作業標準・作業手順書の作成、計画的なOJT、小集団活動といった従来からある手法を用い、一歩一歩地道な改善に取り組むといった姿勢が求められます。画期的な“改革”のような手段は、まずありません。
だからこそ、脳科学の研究から、よりスムーズに技の高度化、客観化ができるヒントを得たいと考えています。自分は脳科学者でも臨床精神科医でも何でもないので、たんに“あったらいいな”という希望を述べているに過ぎませんが…
※ wordingは“言葉遣い、言い回し”といった意味ですが、ここではやや広い意味でとらえ、言語だけでなくビデオ映像や録音、再現可能な動きを含めたなんらかの客観的な表現手法を含めて指すことにします。つまり、無理すれば言葉にできなくはないが、手間とわかりやすさを勘案するとその一歩手前で止めておいた方が利用価値がある表現もwordingの対象として分類します。“可視化(見える化)”と似た概念かもしれません。
※ 一つだけむりやりこじつけてしまうと、前回の記事「高田瑞穂著「新釈現代文」」で示されている「内面的運動感覚」なるものを発揮することが、ニューロ・ワーディングを的確に進める原動力になるような… (^_^)v
■言語習得の研究に脳科学
地に足が着いていない観測ばかりを言っても仕方ないので、少し現実に戻り、言語技能の習得と脳の関係が研究されている書籍を2冊ほど紹介します。
「脳科学からの第二言語習得論の研究」NIRSによる脳活性化の研究
【大石晴美(著)、2006年、昭和堂】
一言で言うと「日本人が英語のリスニングとリーディングをしたときの脳血流の活性度合いを測った実験結果」を解説した専門書です。NIRS(光トポグラフィー)を中心にいくつもの実験がされていますが、その実験結果からは例えば次のようなことが見出せたとされています。
・上級学習者では、右脳側面より左脳側面の血液増加量の割合が多かった。これは左脳にある「ウェルニッケ野」が活発に活動していたことを示唆している
・(短期記憶をつかさどる)前頭葉と(言語野がある)左脳側面の血流増を比較すると、中上級学習者は前頭葉より左脳側面に反応が強かった。上級学習者となると言語野近辺に選択的に血流増加がみられた
・大きくみると、
学習し始めたばかりの初学者…無活性型(どこも反応が鈍い)
初学者~中級学習者…過剰活性型(脳のあちこちが反応している)
中級以上の学習者…選択的活性型(言語野に限って強く反応している)
上級…自動活性型(強く反応する部分はかえって少なくなっていく)
「日本語は論理的である」
【月本洋(著)、2009年、講談社刊】
昔も今も「日本語は論理的でない」という誤解が時々語られますが、言語である以上、そんなことはまずありません。もし論理的でない日本語が蔓延しているとすれば、それは日本語の特性からくるものではなく、使う人の姿勢や教育の問題といえるでしょう。本書は、そのあたりを確かめながら、脳科学の視点から日本語の特性や教育論について解説している本です。脳測定の話が多数出てきます。
以前から研究結果として知られていたこと(角田仮説)をあらためてMEG(脳磁図計)などによる実験をした結果、次の事実が確認できたとされています。
・日本語(やポリネシアの言語)を母国語とする人は、母音を左脳で聴く
・英語人をはじめ他の多くの言語を母国語とする人は、母音を右脳で聴く
その他の検討と併せ、次のような考え方ができるとしています。
・人は発話開始時に最初に母音を「聴覚野」で聴く
・「自分と他人を分離して認識する」概念は右脳の聴覚野のすぐ隣で処理される
・右脳で母音を聴くと「自他分離」を処理する野が刺激され、人称代名詞などを多用しやすくなる
・左脳で母音を聴く日本人(やポリネシア人)はその逆に、自他の識別を示す言葉を積極的に使わない傾向がある
これが日本語で主格(主語)が省略されやすい仕組みだとしています。著者の主張については専門家からの異論も相当あるようですが、あくまで一つの仮説として考えるなら興味深い内容といえそうです。
■将棋名人の頭の中は
これらの研究とはまったく別のものですが、将棋の羽生善治名人を被験者の一人にして、脳活性の様子をfMRIで観察した研究がされています(理化学研究所脳科学総合研究センター)。fMRIに入ったままで詰め将棋などを解き、脳の反応を測定したものです。NHKの番組でも採り上げられたのでご存知の方も多いかもしれません。(NIRSではなく)fMRIなので脳の具体的個所や深部まで測定できています。結論として次のようなことが導けたとされています。
・アマチュア棋士は、前頭前野を中心に活性化がみられた
・プロの棋士は、脳のもっと深い大脳基底核尾状核が活性化した
・さらに羽生名人の場合に限っては、海馬にある嗅周皮質や脳幹にある網様体が活性化していた
ようするに何かを深く極めていく過程で、短期的な記憶→長期的な記憶→習慣的な行動や思考→本能的な行動や思考、へと脳内で主に働く部分が変化(高度化・自動化)していくことが示唆されます。常識と照らし合わせても十分納得できる仕組みでしょう。
* * *
言語技能や将棋の技能に限らず、高度な技を身に付けた人は、きっと頭の中の活性個所が初心者とも中級者とも異なることでしょう。また、技の伝承が得意な人は、理にかなった言葉の使い方や見せ方ができるものと推測します。
この分野についてもっと詳しい方に、ぜひご意見を伺いたいところです。