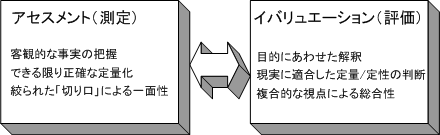宇宙飛行士の人選、育成、組織は、実に興味深いものがあります。

「月の記憶 アポロ宇宙飛行士たちの『その後』」
【アンドリュー・スミス(Andrew Smith)著、鈴木彩織訳、2006年刊、ソニー・マガジンズ】
■月を歩いた人類はわずかに12人
21世紀になって70歳を超えようとするアポロの“ムーン・ウォーカー”たち(12人中、存命の9人)に再び焦点を当て、彼らアポロ宇宙飛行士たちの生き様をインタビューおよび周辺取材でまとめたものです。エッセイともノンフィクションともいえる書物になっています。個人的には、「宇宙」というテーマだけでなく「人材マネジメント」という視点から興味深く読みました。
原題は「Moondust」(2005年刊)。もちろん「人材」のあり方をテーマに書かれているわけではありません。宇宙飛行士をヒーロー視する物語や宇宙飛行士本人たちの自著による直接的な発言と違い、40代半ばである著者が当事者とは少し離れた視点で描いています。読んでみるとなかなか新しい発見がありました。
■宇宙機関はすばらしい組織モデルか?
本書の内容から少し外れますが、以前から私は1つの問題意識を持っていました。それは、
・NASA(アメリカ航空宇宙局)をはじめ宇宙飛行を実現させていく組織は、どんな人材管理(Human Resource Management)システムを築きあげたのか
・宇宙関連機関は、どんな優れた人材養成プログラムを持っているのか
・宇宙飛行士たちは、なぜ皆すばらしい人格と能力を身につけることができたのか
などです。
たとえば日本人宇宙飛行士の毛利さん、向井さん、土井さん、若田さん、野口さんといった方々のTVなどで報じられる人柄や振る舞いには、いつも感銘させられます。肉体的にも精神的にも強く、確実に実績を残していく。一般向けに話す内容は科学的な説明であっても実にわかりやすく、それでいて人間味のある暖かな話しぶりが魅力的です。何度同じような(つまらない)質問をされても笑顔を絶やさず、丁寧に対応していく。しかも驕りのようなものはみじんも感じられない…。
一般企業の人材マネジメントに携わることもある者にとって、こうしたすばらしい人材を選んだり育てたり、組織システムとして実現するためのヒントを、宇宙機関や宇宙飛行士たちから探したくなるのです。
しかし一方で、NASAにしても旧ソ連/現ロシアの宇宙機関にしても、きれいごとではないドロドロの顛末が過去にあったことが明らかになっています。映像化された「人類月に立つ」「ライト・スタッフ」「ロスト・ムーン(アポロ13号)」「宇宙へ ~冷戦と二人の天才~(スペース・レース)」といった映画やドラマを見るだけでも、たとえば
・月着陸という冒険が、今から考えると実はとんでもない高いリスクのもとで敢行されたプロジェクトであったこと
・NASA内部のいざこざおよび政治の世界との軋轢は絶えず、どう見ても健全な組織運営とはいえなそうな現実があったこと
・宇宙飛行士たちは「人格者」「ヒーロー」といったイメージからはかなり外れた、どちらかというと欠点が目立つ人たちであった(らしい)こと
などが見てとれます。
ほかにも米国や旧ソ連の宇宙競争を描いた書物や映像、宇宙飛行士自身によるエッセイなどいろいろ出ています。とくに「ドラゴンフライ―ミール宇宙ステーション・悪夢の真実)」では、宇宙ステーションミールに滞在していたスタッフの人間関係が一時期相当に険悪だったことが暴露されています。2003年のスペースシャトル・コロンビア号の空中分解事故では、NASAという組織の体質が重大事故を引き起こした大きな原因だったと事故報告書で指摘されました。日本のJAXA(宇宙航空研究開発機構)およびその前身だった組織も、ロケット打ち上げ失敗などでさんざん非難を浴びています。
いったい、宇宙飛行士および宇宙機関の実像はどんなものなのでしょうか?
■付き合いにくそうな人ばかり…
少し偏った表現かもしれませんが、本書で登場する宇宙飛行士9人のうち“常識的なコミュニケーションがとれる魅力的な人”と感じられるのは、アラン・ビーンとチャーリー・デュークの2人くらい。あとの人たちはおしなべて“いかにも人付き合いの難しそうな”輩ばかりです。
バズ・オルドリンは、一時期深刻な鬱病だったことが知られています。とても気難しい雰囲気が漂ううえ、「一言一言、慎重に言葉を発するのだが、…(中略)…独特の文法のせいで話の筋があちこちに逸れて、何を言っているのか理解するのに時間がかかる…(後略)」(上巻p.209)とあるように、著者がインタビューでいかにも苦労したことがわかります。著者は最後に「疲れ果てた」とさえ書いています。インタビューの最後は信頼感も築かれたのか、著者は「本物の好意と賞賛の気持ちがこみあげた」(上巻p.244)ようですが、誰とでもそうした緊張の解けた付き合いができる人ではないことがはっきり読み取れます。
ジョン・ヤングは、アポロより前のジェミニからつい最近のスペースシャトルまで現役の宇宙飛行士を続けた、それこそ全地球人を代表する“最も経験のあるプロ宇宙飛行士”でしょう。ところがヤングとのインタビューもこれまた大変気を使わなければならなかった様子が描かれています。大変博識でかつ強靭な人であることはすぐにわかるし、結果的に非常に興味深いことをあれこれ話しているのですが、一つ間違うとまともに口を開かなそうな頑固な様子が感じられます。
“最初のムーン・ウォーカー”ニール・アームストロングにいたっては、どんな取材も受けないのが鉄則で、本書の著者も最後まで追いかけ続けたあげく、イベント会場での短いやり取り以外はついに長時間のインタビューができずに終わってしまったようです。もともと相当の口下手で朴訥、それでいて独断で物事を判断する傾向があるといわれていました。月着陸で世界中から注目された後は、隠遁生活といってもよいほど世間から逃れてすごしているそうです。
・アラン・ビーン(アポロ12号月着陸船パイロット)
・チャーリー・デューク(アポロ16号月着陸船パイロット)
・バズ・オルドリン(アポロ11号月着陸船パイロット)
・ジョン・ヤング(アポロ16号船長)
・ニール・アームストロング(アポロ11号船長)
■競争が好きではない? 宇宙飛行士もいた
もっとも、アポロより前の初期の宇宙飛行士たち(マーキュリー計画やジェミニ計画を引っ張ったいわゆる「オリジナル7」のメンバーなど)はもっと強烈な個性を持っていたともいわれます。むしろアポロで何人かの常識人がいたということは、この頃はNASAの人材マネジメントも少し進歩していたのもしれません。
アポロ宇宙飛行士の中で人間的な魅力をとくに感じさせるのは、アラン・ビーンでしょう。ビーンはNASAをやめた後芸術家に転進し「月面での体験を描くアーチスト」として活躍しています。インターネット上の Alan Bean Gallery に作品が紹介されています。ドラマ「人類月に立つ」を見たことのある方は、ビーンを語り手にしてクルーのチームワークを描いたアポロ12号の回のことをきっと覚えていることでしょう。
アラン・ビーンは、名誉ある役を我先に得ようとする野心家揃いの宇宙飛行士の中で異質な存在だったようです。他のライバルに比べると競争というものにさほどこだわっておらず、“たまたま4番目に月を歩く役が回ってきた”だけだという。月から帰ってきてからも競争を引きずっている過去の仲間たちについて一歩引いて見ている様子があります。アーチストになって、他人と競争するのではなく、自分で「何かをやってみて、それがうまくいくかどうかを見ているほうが良い」(下巻p.60)。この言葉は必ずしも本音とは異なるのかもしれませんが、そんな彼が、結果的にたった12人しかいないムーン・ウォーカーに選ばれていたということは面白いですね。
もう一つアラン・ビーンの話で興味深いのは、宇宙での行動もさることながら、最も感じるところがあった出来事が「月から帰ってきたあとの地球上での日常生活だった」という点です。「ショッピングセンターでアイスクリームをなめながら何時間も座って周囲を眺めていた。その光景に対して、月旅行に負けないくらいの胸の高鳴りを覚えた…」といいます。
■アポロ宇宙飛行士に求められた資質とは?
本書にもありますが、クルーの人選は当時の宇宙飛行士室長ディーク・スレイトン(「オリジナル7」の1人だが、7人のメンバーのうちマーキュリー計画で唯一宇宙に出られなかった人物)が強い影響力を持っていたことが良く知られています。そのため、ディーク・スレイトンに好かれれば宇宙に旅立てる可能性が高くなり、疎まれれば絶望的といわれていました。
実際、何人かのメンバーはスレイトンの逆鱗に触れてその後一切メンバーに選ばれなくなったとか伝えられています。システマチックな人選とは程遠く、公平な人材マネジメントとはとてもいえそうにありません。こうしたアポロ時代の人選・人材養成のシステムと現代の宇宙飛行士たちが選ばれ養成されるシステムとのギャップは、私にとってずっと謎でした。
しかし本書から、これに関連した面白い記述を2つほど見つけました。芸術家肌のアラン・ビーンは、クルーの人選に大きな力をふるっていたスレイトンに必ずしも高く評価されていなかったらしい、というのが1つ。それでもビーンが選ばれたというのは、やはり1人の人の好き嫌いだけに左右されない、何らかの選抜基準があったということなのでしょう。
■「想像力をしっかりと封じ込める力」
そしてもう1つは、「船長」と「月着陸船パイロット」の役割の違いが人選に影響していたらしいという点についてです。
船長はまさにミッションを成功させるためのすべてについて責任を持つべき立場の人間。それに対して月着陸船パイロットは、もちろん責任という点でも実際の飛行業務でも大変重要であることは間違いないのですが、月着陸についてさえも最終的には自分ではなく「船長」が責任を持っていたわけです。そのため、船長に比べると少しだけ本来業務から離れたことを考える余裕があり、その分「感動」を目の当たりに体験できる立場にあったとされています。
エドガー・ミッチェル曰く、「自分たちが強烈な体験をしたと口にしていたのは月着陸船パイロット。船長は自ら責任を持って操縦する役割を持っていた」(下巻p.331~)。著者はこれらから、ディーク・スレイトンが選ぶ船長の条件として「ずば抜けた集中力と、想像力をしっかりと封じ込める力があること」と推測しています。もっと端的にいえば「冷徹な人」になれるかどうかが、アポロのような仕事に必要だったことをうかがわせます。
・エドガー・ミッチェル(アポロ14号月着陸船パイロット)
■人間臭さと職務の役割
これがどこまで本当かはわかりませんが、ニール・アームストロング、デイビッド・スコット、ジョン・ヤング、ジーン・サーナンのいずれもが「逡巡や動揺といった感情を持ちそうにない性格の人々だ」としています。すでに亡くなったアラン・シェパードとピート・コンラッドについてははっきり言及していません。
半面、この「船長」たちは皆敬意を抱くことのできる優秀な人たちではあるが、揃いも揃って人当たりは悪いか、少なくとも気の置けない仲間といった存在ではないわけです。隠遁してしまったり(アームストロング、スコット)、逆に「昔、ほんのひととき月を歩いた」という名声を利用して活躍する、自らを脚色しているような、鼻に付く存在だったりします。いずれも、周囲の人から見てあまり評判が良いとはいえません。
一方バズ・オルドリン、アラン・ビーン、エドガー・ミッチェル、ジム・アーウィン、チャーリー・デュークといった「月着陸船パイロット」たちは、信仰の道に入ったり、芸術家になったりと、月に行く前の宇宙飛行士としてのキャリアからは直接的に想像できない道を歩んでいます(ジャック・シュミットは、ムーン・ウォーカーの中で唯一学者出身なので、ちょっと事情が違う)。このグループにも人あたりの必ずしも良くない人(オルドリンがその代表)もいますが、そうであっても、インタビューから垣間見られるそれぞれの人柄や生き様はじつに人間臭さが漂っていることがわかります。
・ピート・コンラッド(アポロ12号船長)
・ジーン・サーナン(アポロ17号船長)
・アラン・シェパード(アポロ14号船長)
・デイビッド・スコット(アポロ15号船長)
・ジム・アーウィン(アポロ15号月着陸船パイロット)
・ジャック・シュミット(アポロ17号月着陸船パイロット)
■すぐに結論を求めすぎるな
ほかにもいくつか、本書を読んでいてはっとさせられる記述がありました。
「すぐに結論を求めすぎるな」
「宇宙飛行士だって怖いもの知らずというわけじゃない。恐怖感を克服して目の前の仕事をやりおおせる方法を見つける」
「月に行った経験を話すだけで高慢になることがある。でもそれはうぬぼれだ」
など。いろいろ示唆に富んでいます。
なお、この本の欠点は、構成や文章がかなり冗長なことです。たとえば宇宙飛行士へのインタビューにしても、インタビューそれだけでなくアポをとる過程とか昔話とか著者の回り道が非常に多く、なかなか本論に入らないので飛ばし読みしたくなるところが何個所もあります。テーマをきちんと整理して核心をもっとコンパクトにまとめれば、1/2から1/3くらいのページ数で済み読みやすくなるでしょう。
でも、インタビューの骨子を簡潔にまとめる手法ではなく冗長にあれこれ描写しているところが、出てくる人物の人間味とかとっつきにくさとか時代背景との関係とかを浮かび上がらせているともいえそうです。その意味で「すぐに結論を求めたくなる」我々を、わざと遠回りさせることに成功しているのかもしれません。
本書からあえて人生訓のような結論をとりだすのなら、「人生の勝利」というのが、決して名声や富を得ることではなく、またスピリチャルになることでもなく、困難を飲み込み克服していくことのような気がしました(あまり適当な表現ではありませんが…)。
■中年ビジネスパーソンにとっての「人生の見直し」?
あとがきで訳者が「“中年の危機”を意識するようになった作者が、帰還後に世間の荒波に放り出されることになった宇宙飛行士たちの生き様から有意義な教訓を得られるのではないかという期待をこめた旅」と評しているのには、ニヤリとしながらも、自らギクリとさせられてしまいました。著者は、10歳前後で月着陸のニュースに感銘を受けた世代。この文を書いている私もまさに同世代です。
たとえば、これまで懸命に働いてきたものの、時代の変化があり企業組織で半ば居場所がなくなった40代くらいのビジネスパーソン、リストラや転職という転機があったがまだ定年までには時間があり中途半端な今後に不安を抱いている中年。そんな方々には、「宇宙飛行士の」というより「著者の」危機意識がいろいろ伝わってくると思われます。