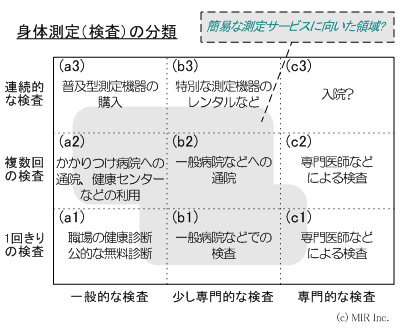宇宙ステーションで起こるいくつもの争いを冷静に見てみると、それは現実社会(企業社会)で起こる人間関係の縮図のような気がしてきます。

「ドラゴンフライ ― ミール宇宙ステーション悪夢の真実」(上)(下)
【ブライアン・バロウ(著)、北村道雄(訳)、寺門和夫(監)、筑摩書房、2000年】
「ドラゴンフライ」1-宇宙飛行士の“問題児”たち の続きとして、宇宙ステーションでの人間関係について少しご紹介します。
宇宙飛行士個人の諍いについてあげつらうつもりは毛頭なかったのですが、やはり気になる話題がたくさん出てきます。あらためてこの本を読んでみると、宇宙ステーションという特殊な閉鎖空間の話というより、我々のごく日常的な生活の中で起こる問題が分かりやすい形で切り出されたきた話のように思えます。
■問題に慣れると問題の存在を忘れるようになる
米側の宇宙飛行士は、ミールに入ってすぐ、船内が相当ひどく散らかっていたことに驚かされました。それまでの宇宙生活でたまった残骸(小型コンピュータ、事務用品、道具、音楽テープなど)が、無重力の部屋のあちこちにあったそうです。
また、ミールのモジュールとモジュールが何本もの太いケーブル(換気チューブとか通信ケーブルとか)で無造作に結んであるため、モジュールの間のハッチを閉めることができなくなっているところがありました。万が一あるモジュールで機体破損などの事故が起こった時、他のモジュールまで波及し全滅しないように、途中のハッチを完全に閉めて隔離しなければなりません。ハッチを閉めるためには、数多くのケーブルを無理やり切断することになります(事実、貨物船プログレス衝突事故でまさにその通りの事態が起こった)。
そんな安全上の不安を米側の宇宙飛行士が口にしても、ロシア側の反応はいつも同じで「一応耳を傾けはするが、結局そのまま無視」だったされています。NASAも結局は同じような反応でした。
このあたりの反応(一応耳を傾けはするが、結局そのまま無視)は、ビジネスパーソンなら、というより社会の中でなんらかの組織・グループで活動をした経験のある人なら誰でも、かなりはっきりイメージできるのではないでしょうか。問題を指摘しても、その問題に慣れてしまうと誰も解決しようとしなくなる…。
■優秀な飛行士も、時と場合により問題児になる
ミール・ミッション(フェイズ1)の米側飛行士7人のうち「問題を起こした数人は“問題児”」と前回書きましたが、ジェリー・リネンジャーなどと違い、ジョン・ブラハはNASAではかなり優秀な宇宙飛行士の一人だったようです。それでも彼のミール・ミッションの4カ月は、本書の記述をそのまま受け取れば失敗だったと思わざるを得ません。
ブラハは体力、精神力とも優れ、それ以前のスペースシャトルで船長まで務めたベテラン宇宙飛行士でした。話によると几帳面すぎるほどしっかりと仕事をするタイプの人だったようです。“でも”というべきなのか、“だから”というべきなのか、ミール・ミッションの混乱した仕事の進め方には耐えられませんでした。
彼自身、有能だとはいえ「他の人に、はなはだしく依存する性格がある」ことが、ロシア側が行った性格検査(アセスメント・テスト)から事前に見て取れたといいます。その詳細までは書かれていませんが、推察するに「箸の上げ下ろしも部下や秘書がやってくれるような条件の上で本来の力を発揮できる“お殿様”的リーダー」だったのかもしれません。
そんな人、我々のまわりにもたくさんいますね。「大企業の社長は務まるかもしれないが、実働メンバーの立場になると何一つできない」「公の場では威張っているが、家庭では家人なしにお茶さえ自分で入れることができない」なんていうタイプの人が…。
また、ちょっとしたコミュニケーションのミスで、ミールのロシア人船長ワレリー・コルズンと怒鳴りあいになったそうです。無駄に30分くらいの時間を費やすことになってしまい「あんたのせいで35分も時間を無駄にした…」などと怒り狂ったといいます。こんな人(先輩)も現実の企業世界にいますよね。とくに有能とされる人に多く…。
そんなブラハが、時にはワレリー船長から「アメリカ人なら幼い孫にしか使わないような口調で命令された」といいます。長い共同生活がずっとその調子では、自らのペースをつかみようもありません。
■「まさか私が鬱病になるなんて…」
そんなロシア人に悩まされるよりもっとブラハを苛立たせたのが、米側のサポート体制だったといいます。訓練期間中、ロシア語の習得に費やされた時間はわずか4カ月しかありませんでした。仕事のマニュアルをめぐって、出発前から繰り返しヒューストンと対立します。「何かを求めても結局実現されないやりとり」が繰り返されるとどうなるか。“被包囲心理”、つまり「周りは敵ばかりだから、何もかも自分でやらなければならない」という心理状態が強くなり、結果的に気持ちがどんどん内へ向かうことになります。
それでいて、ヒューストンはブラハを完全に自分たちのコントロール下に置くことを疑わず、運用管理者にそれを求めます。両者の認識の違いは広がるばかり。ついにブラハは、ミール内で鬱病にまで陥ってしまいました。
「つねづね自分のことを、物事を前向きに考え、ほかのクルーが気落ちしているときに元気づけてやるタイプの人間だと思っていた。その自分が鬱病にかかるなんて理解しがたいことだった」(上巻p.188。文面は多少変更)。そんな告白を他人事ではないと感じる方もまた、少なくないでしょう。
■現場を知らない本部管理職にコントロールされる恐怖
この経過を現実のビジネス社会になぞらえ、勝手に次のような喩え話にしてみました。
・本社が、支店の営業力向上のため、本社の有能な「幹部」を支店に派遣する
・その「幹部」は、支店では営業現場の最前線で力を揮うことが期待されている
・「幹部」は有能だが、周囲に部下の手足があってこそ力を機能するタイプの人である
・しかし実際には「幹部」に手足となる部下はなく、仕事の手順書もなく、支店の文化も非常に異なる
・「幹部」は支店の現場が頼れないと悟り、本社に手順書などの作成を要望する
・しかし本社はその要望の真の意味が分からず、本社の認識を基本に「幹部」に指示を出し続ける
・「幹部」は本社もあてにならないことを知り、自分流の仕事の進め方に頼る。そして1週間に7日懸命に働こうとする。いちいち細かい動きを本部に伝えても無駄と感じられて、報告も滞る
・しかし本社は、本社の方針に沿って「幹部」に成果をあげてもらわなければならないから、監視役をたてて「幹部」を完全なコントロール下に置こうとする
・せっかく苦労して「幹部」が支店の営業現場に即した仕事の進め方を実行しようとしても、本部は認めず足を引っ張るような結果となる。
・「幹部」は自らを否定されたような立場になる
・本社との溝も、支店の他のメンバーとの溝も、いずれも深まるばかり。しかしそれでも我慢して続けなければならない立場に追いやられる
真面目な人であればあるほど、精神に支障をきたすことになりそうです。そんな話も、この現実のビジネス社会でたくさんありますね…。
■短距離走のつもりで長距離走は走れない
NASAの地上管制官への不信感もあり、ブラハが次の“問題児”リネンジャーに引き継ぎをするとき「地上からの支援はあてにするな。ここで頼りになるのは自分だけだ」とか警告していたそうです。それが今度はリネンジャーの“唯我独尊”を助長してしまうのですから、まさに悪循環です。
ブラハについては、一緒に訓練を受け気心の知れたロシア人クルーたちとはむしろ良い人間関係を作ることができたとしています。ブラハがもとから“問題児”だったのでは決してなく、ミール・ミッションという仕事のシステムとか、与えられた職務内容とかが、とことんブラハに適合しなかったために生じた摩擦といったほうがよいのでしょうか。ブラハに限らず、ミール・ミッションに関するNASAの人選や育成方法は失敗続きでした(誰もミール・ミッションに参加したがらず、他に人選の余地がなかったという現実があったにせよ)。
少し違う視点から見ると、シャトルの1~2週間という「短距離走」と、ミールの3~4ヵ月という「長距離走」の違いということもできるようです。短距離走しか参加したことのない米宇宙飛行士が、同じ流儀で長距離走に参加しようとしてもだめでしょう。短距離走者の育成・コーチ・コントロールしかしたことのないNASAが、配下の選手を長距離走の選手になるべく無理やり選抜・コーチ・コントロールしようとしても失敗するでしょう。ペース配分や考え方自体が、相当に異なっていたのかもしれません。
—
それはそうと、今まさにスペース・シャトル(STS-115)によるISS(国際宇宙ステーション)組み立てミッションが進んでいます。
また、近い将来ISSに搭乗する予定の若田宇宙飛行士が、ISSでの滞在を念頭に、米国の潜水艦に滞在して閉鎖空間での長期間生活訓練を受けていると伝えられています。若田さんはすでに何度か閉鎖環境テスト(「中年ドクター 宇宙飛行士受験奮戦記」でもちらと書きました)を受けたはずですし、実際の宇宙飛行も経験済みです。さらにロシア語も習得済み。ロシアの星の街・訓練センターでの訓練も経験済み。なのになぜまた今さら閉鎖生活訓練を受けるのだろうと、初めは少し疑問を持ちました。
でも本書に書かれているようなスペースシャトルと宇宙ステーションの決定的な違いを読むと、あらためてはっきりその背景や意味が納得できるような気がします。