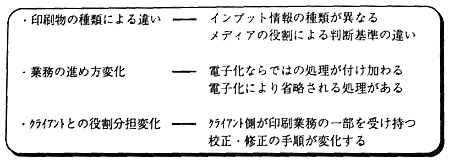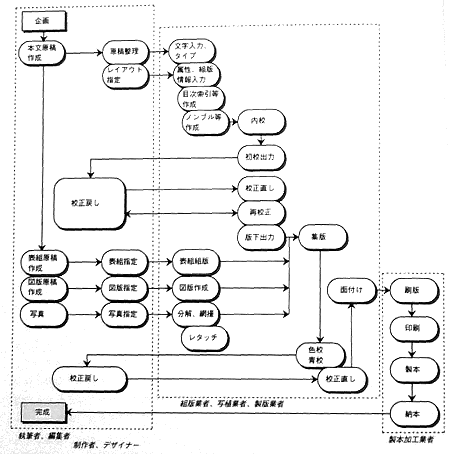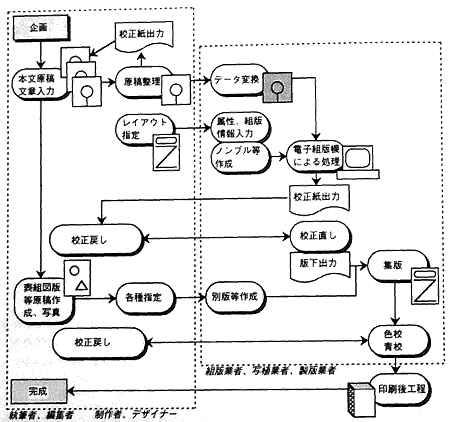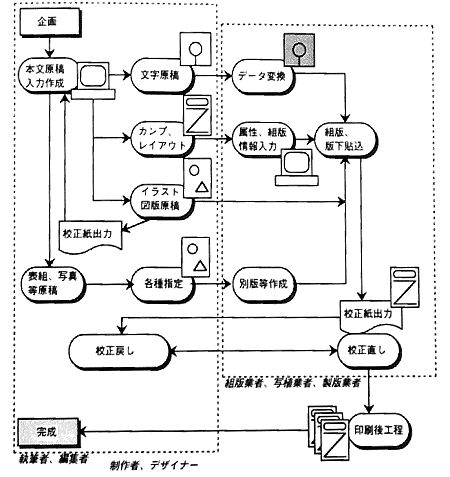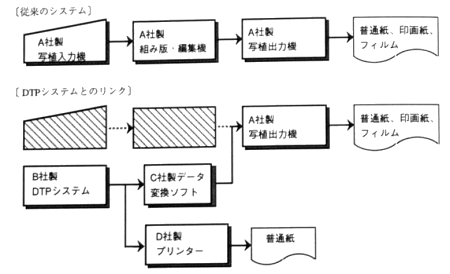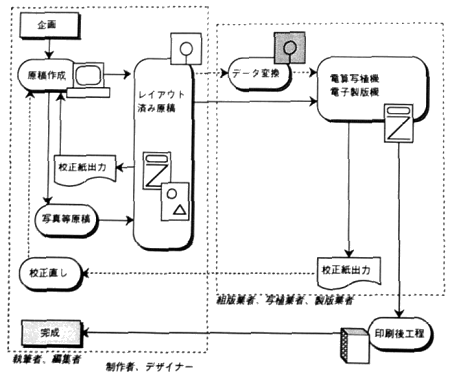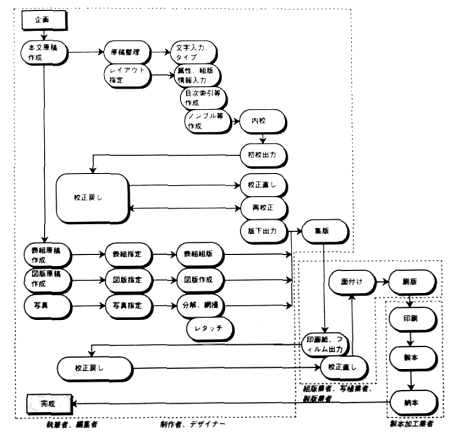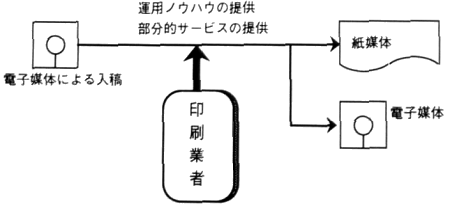印刷工程の電子化、システム化により、印刷の流れがどのように変化したのかを考えます。
第2章 システム導入の方法 2-1 コンピュータ化の分析■電子出版の“複雑化要素”
第1章ではフロッピー・ディスクを顧客から持ち込まれたケースを紹介した。この場合、データ変換ソフトを使ってフロッピー・ディスクの中の文字データを電算写植システムにインプットできるデータに変換しただけで、一応の解決をみている。しかし、一般に印刷電子化に関わる事態はもっと複雑である(図2-1)。――― 図2-1 電子出版を複雑にする要素 ―――
まず、印刷物の種類によってインプットすべき情報はかなり異なる。書籍の場合文字要素が大半で、レイアウトはページごとにそれほど違いがない。雑誌は文字のほか図版や写真が複雑に組み合わされるものが多いため、文章、図版、写真、レイアウトなど、インプットすべき情報は多様である。チラシやパンフレットのような商業印刷物の場合、文字情報は少ないが文字書体や配置に表現力が要る。商品カタログでは、文字や写真が重要な要素を受け持つのみならず、商品データベースとしてデータ間の関係が情報として提供されないと困る。単にフロッピー・ディスクに入っているデータを変換すればすむ話では決してない。
次に、電子化に即した業務の進め方を新たに検討する必要がある。例えばデータ変換ソフトによりデータ処理するならば、従来あった「文字入力」という作業は省略されるものの「変換作業」という新たな処理が付け加わる。さらに、ワープロの文書データから文字要素を変換することが出来ても、組み版やレイアウトに関係する情報は十分でない(あるいは全くない)のが普通である。単に文字入力オペレータを“変換オペレータ”に鞍替えさせればすむというわけではなく、足りない情報を補う(または生成する)ための手順を作り込む必要がある。誰がどの時点でその処理を実行するのか。プラスアルファとマイナスベータを見極めなければならない。
クライアントとの役割分担にも注意する必要がある。フロッピー入稿は「文字を並べる」という作業が印刷業者の手から顧客の手に移行することを意味する。DTPシステムの利用で顧客側がレイアウトまで終わったデータを印刷業者に受け渡すとしたら、組み版、割付の役割も顧客に移ることになる。となると、いつどのようにしてこれらの情報が提供されるのか、納期や品質の面で不都合はないかなどを考慮しなければならない。特に印刷には付き物の校正作業をどうおりこむかが重要で、修正があった場合にどちらがどのように反映させるのか前もって定めておかないとならない。クライアント側が修正処理をすると思い込んでいたものが修正されないまま残り、最終段階でのっぴきならないトラブルを引き起こすことが往々にしてありうる。せっかくのコンピュータ・システムも機能せず、むしろ疫病神になりうるわけだ。■印刷工程を整理する
図1-1では印刷システムのごく簡単な概念図を示したが、ここでは先に挙げた“複雑化要素”が明確になるよう、印刷物が生産される過程でどのような作業が行われるかをリストアップしよう。図2-2に一般的な印刷物作成工程を分解した業務フローチャートの例を示した。このフローチャートは、紙媒体をインプットし紙媒体にアウトプットする従来型の印刷の世界のものである。ただし、電子組版機や電算写植機は利用できる環境を想定しているため、例えば「本文入力」「組版情報入力」というモジュールで工程を表現している。手動写植機や活版印刷、タイプオフはそれぞれ工程が異なってくるが、コンピュータ化に関わる考え方の基本は同じなので、読者によってフローチャートの中身を適宜読み変えていただけたらありがたい。
なお、印刷物の種類によっても作業の流れはかなり異なるので、以下の説明においてはできるだけ印刷物の種類も特定させながら、種類別にフローチャートを提示することにする。――― 図2-2 一般的な印刷物作成業務のフローチャート例 ―――
図2-2中央に、組版から製版まで印刷業者が受け持つ範囲が広がっている。業者にインプットされるものは、手書きの原稿とレイアウト情報、表組みや図版、写真の原稿と指定情報である。原稿用紙に書かれた本文をオペレータが組版システムに入力しながら、ファンクション・コードや属性情報を埋め込む。この結果を棒組なりページ組なりで出力する。同様に、表組は非常に複雑なプログラミングをする感覚で情報を入力、別版として出力する。図版についても、写植打ちするものはバラ打ち文字や線画図形として作成する。各コンポーネントが出来上がれば、版下貼込が行われる。
この過程で、何度もクライアント側に校正紙を出したり戻したりしながら、チェック・修正が繰り返される。実際には、図の矢印ではとても足りないほど打ち合わせもしくは校正紙のやりとりがされることになろう。校正以外でも、入力から出力にいたる各工程は複雑に絡み合っている。作業のフローチャートを詳細に書くとあまりに矢印が交差しすぎて分かりにくくなるため、精密にし過ぎることは避けている。
写植、版下段階の校正が終われば、写真と組み合わせて製版が行われる。この段階で写真のレタッチ、網撮りなども必要に応じて行われている。
アウトプットは業者によって異なるが、この図では製版用フィルムを想定した。業者によって完全版下が納品されたり、印刷製本機能を持っていれば最終的な完成品が成果物として顧客に戻されることになる。■電子化による流れの変化
さて、この従来型の印刷工程にコンピュータや電子データが入り込むとどのようになるか、いくつかの状況設定をしてその様子を見てみよう。●例1:フロッピー入稿による書籍制作
〔仮定:組版から写植版下出力を行う業者が書籍の版下制作を行うと想定。本文はフロッピー・ディスクで入稿するが、図版や表は手書き原稿。業者は写研製の電子組版機と電算写植機、汎用のパソコンとデータ変換ソフト(コンバータ)を装備〕第1章でも紹介した、文字データをデータ変換ソフトを通じて電算写植機へもっていく、最も基本的な例である。
――― 図2-3 例1(フロッピー入稿)のフローチャート例 ―――
このケースの業務フローチャートを図2-3に示した。刷版以降の印刷工程については「印刷後工程」として省略してある。
図2-3では、図2-2と比べて文字(文章)の入力が業者の役割から発注者の役割に移っていることがわかる。代わりにデータ変換の作業が必要だ。ここで大事なのは次の3点である。
(1) フロッピーで渡されたデータを正確に写植用データに変換できるか
(2) 文章情報以外の各種属性、組版情報などをどのようにいかに正確、迅速に追加するか
(3) 文字や体裁の修正をどのように扱うか
(1)については、見かけは同じフロッピー・ディスクであっても、ワープロごと、パソコン・ソフトごとにデータ格納フォーマットが異なるので、「どのワープロ(パソコン・ソフト)を使って作成したものであるか」を発注者側から正確に聞き出さなければならない。しかも、ワープロの細かな型番やソフトウエアの細かいバージョンまで特定しなければ、データ変換が出来ない危険性がある。「フロッピーをもらってきたがその中身がどの機種で作られたデータであるかが分からず、結局打ち出し原稿を見て文章を入力し直すはめになった」などという冗談のような光景が、実際にあちこちの印刷会社でみられたと聞いている。
加えて、そのフォーマットのデータを目指す電算写植機(ここでは写研製)のデータに変換できる機能を持つソフトウエアを手元に用意しなければならない。現在あるワープロすべての変換ソフトを備えようとすれば、それだけでかなりの数を備えなければならない。ただ、徐々にデータ形式は標準的なものに収束する傾向がある。パソコンでは最も標準的なMS-DOSテキスト・ファイル、および代表的なワープロ専用機数機種からのデータ変換ができれば何とかなるケースが多い。
(2)については少し厄介だ。電算写植機で使われるファンクション形式のデータを作り込むことを仮定すれば、書体や組版情報を指定する各種コマンドやトリガーなどを文章中に正確に付け加えていかなければならないことになる。ここでは文字中心で特殊なレイアウトが少ない書籍の制作を想定しているため写植コマンドの入力はそれほど手間ではないと思われるが、複雑なレイアウトやフォント、特殊な組版処理を必要とする書物の場合、一から文字とともにコマンドを入れていく場合と大して変わらない手間がかかることもありうる。となると、フロッピー入稿で文字入力が終わっているところから出発したと言っても、全体としてちっとも業務効率化にはつながらないこともありうる。
最後の(3)については、発注者側との綿密な打ち合わせが必要である。フロッピー・ディスクで渡す電子データが(このケースでは)文字に限られているので、最終的に書体指定やレイアウトが終わった文書は、業者が電算写植機で印刷してみなければ発注者側には分からない。その時になって文章の入れ替えがあったり、大幅なレイアウト変更が起こったらどのように対処するか。校正を打ち出し(紙媒体)上で行うのかデータで行うのか、発注者が行うのか業者が行うのか、ここをはっきりさせておかないと大きなトラブルが起こりかねない。また、ワープロ入力に伴う誤変換が結構最後の段階まで残りやすい。
発注者側が気を利かせたつもりで修正した文書データを新たにフロッピー・ディスクで持ち込んだとするとどうなるか。前の文章とどこがどう修正されているのかすぐに判然としない場合、新しいデータで「データ変換→書体・レイアウト指定」の処理をまた一からやらなければならないことになる。すなわち、それまでの業者の苦労の大半は徒労に終わったことになり、難しいコマンド埋め込みに精を出さねばならない。むしろ、いったん電子組版機で処理を進めたら、後の修正はよほど大きなものでない限り、校正紙に赤字修正を入れる従来型の校正手順をとったほうが明らかに有利である。ただのワープロ文書では(後で述べるDTPシステムのような仕組みを使わないと)最終的な組版体裁やレイアウト情報を発注者が自分の手で指定できないことに原因があり、結局これが解決できないと中途半端な電子化しかできないことを意味している。■難しい文書レイアウト情報の受け渡し
同じフロッピー入稿でも、例1のように文字中心の印刷物でなく、文字書体、図版、レイアウトといったデザイン情報が決定的に重要となるケースはどうだろう(図2-4)。●例2:1枚ものの商業印刷物(その1)
〔仮定:フロッピーで原稿が受け渡しするが、文字数は少ないパンフレットの例。イラストやカット、書体指定などが重要な要素で、カラー写真も組み合わせて製版する。カンプ(レイアウト)は一応電子的に作成されている。図版の一部もグラフィックス・ソフトで描かれた打ち出しが原稿として渡された〕例1と同様、フロッピーで受け渡されるのは原則として文字情報だけだ(属性情報の一部を変換できる変換ソフトもあるが、一部を除いてそれほど実用的ではない)。データ変換ソフトを通してデータ・コンバートしても、そもそも文字情報そのものが量があまりないのでほとんど役に立たない。パソコンで一応レイアウトされていても、多くのソフトやワープロは独自のデータ形式でレイアウト情報を持っているため、電子組版機に生かすことが出来ない。あくまでもラフレイアウトとして、または手書き代わりのレイアウト指定として役立つだけである。
――― 図2-4 例2、例3、例4のフローチャート例 ―――
となると、データが電子化されている意味はほとんどなく、従来型の手作業による業者の組版、写植処理で作業を進めざるを得ない。省力化できるのは、クライアントがグラフィックス・ソフトで自作した図版を写植打ちせずにすむところぐらいである。
■レイアウト情報を受け渡すには
では発注者が提供したレイアウト済みの文書をそのまま生かすことは出来ないか。言い換えると、発注者が手元のプリンターで打ち出した結果とほぼ同じ印刷結果を電算写植の出力機から得ることは出来ないのか。ここで、発注者側がどのようなシステム、ソフトを利用したかが大変重要なポイントとなる。●例3:1枚ものの商業印刷物(その2)
〔仮定:例2とほぼ同じ設定で、クライアント側がパソコンDTPソフトで最終レイアウトを完成させているとする。ただし、その文書データはページ記述言語の「ポストスクリプト」形式になっている。さらに業者側が、ポストスクリプト対応のレーザー写植機を装備しているとする〕例2で電子化のメリットが出なかったのは、データ形式の不適合が最大の理由である。文字を並べる考え方、レイアウトの思想そのものがパソコンと写植機で異なっているのが根本原因である。
となれば、パソコンと写植機の思想を近付けて、双方が扱える“標準的なデータ形式”を設ければよいということになる。要は、入力からレイアウトを処理する編集機と写植出力機がマッチングできればよいわけである。
DTPシステムによってはレイアウト済みの“標準的なデータ形式”で出力できるものがある。この“標準的なデータ形式”を解読できる写植出力機もある。クライアントが標準データ形式で出力し、印刷業者がそれを解読できるマシンを用意すれば、発注者から受け取ったレイアウト済みの文書を直に写植出力できる。途中、業者が例えば「トンボ(目印)」の追加や若干の調整が必要にする必要が出るとは思われるが、レイアウト済み文書の版下作成の大部分を顧客が“内製化”できることを意味する。
“標準的なデータ形式”とは、主に「ページ記述言語」(Page Description Language:PDL)を指している。「1枚のページ全体をどのようにレイアウトし、どこにどのようなに文字種を並べ、どんな線を引くか」を表現できるデータ形式で、一種のプログラミング言語でもある。うち、世界中で最も普及している(標準的と言える)PDLは米アドビ・システムズ社が開発した「ポストスクリプト」(PostScript)で、アップル・コンピュータがDTPシステムの提唱に成功したのも、このポストスクリプトの存在が大きな役割を担っていた。米国では、DTPからみのソフトウエアのほとんどはポストスクリプト出力ができる。
写植機では、ライノトロニック(独ライノタイプ・ヘル社)やバリタイパー(米バリタイパー社)がポストスクリプト対応として有名である。ライノトロニック、バリタイパーとも当初は欧文書体しか対応していなかったが、ポストスクリプトの日本語対応が実現したことを受けて日本語フォントを搭載し、国内写植機メーカー、モリサワの日本語フォントなどを利用できるようになった。
図2-4で言うと、印刷業者に受け渡される情報(文字原稿、レイアウト情報、イラスト・データ)がポストスクリプトのデータになっており、印刷業者がポストスクリプト対応の出力機を持っていれば問題は解決する。
もっともこのマッチングさえできれば、データ形式はポストスクリプトである必要はない。ESC/Page(セイコーエプソン)やLIPS(キヤノン)と呼ばれるパソコン用プリンターの制御コマンドもページ記述言語の仲間として位置づけられるし、代表的なCAD(Computer Aided Design:コンピュータに支援された設計)ソフトのデータ形式(例:「DXF」)やワープロ・ソフトのデータ形式(例:「RTF」)もそれぞれ“標準的なデータ形式”候補といえる。しかし、いずれも写植・組版システムと組み合わせるには一長一短があるため、写植出力機側で対応しているものは少ない。日本の印刷事情に合わせた標準データ形式の策定を提唱する動き(シンプルプロダクツなど)もあるが、標準化や普及はこれからである。ポストスクリプトでなくて構わないとは言うものの、入力から出力まで一貫した標準化がなされているものと考えれば、今のところやはりポストスクリプトが最有力だ。■写研製写植機との連係
ライノトロニックなどがポストスクリプト対応でオープン化を進めたのに対し、これまで日本の写植機メーカーは各メーカーが独自にシステムを専用機として構築してきた。オープンな思想が薄かったのは否めない。そのため、汎用のコンピュータとの接点がなかなか見いだせないというのが本当のところである。特に、メーカー最大手の写研はこれまで自社のフォントを他メーカーに提供することは一切行っておらず、ポストスクリプト対応写植機に限らず、他社の出力機から写研フォントを使った出力はできない。例3ではモリサワ製のフォントは印刷できるが(将来写研がポストスクリプト用フォントの提供をすることがなければ)写研製フォントの出力は得られない。
しかし、うまく日本製電算出力機へのデータ転送ができるよう技術的に工夫すればよいわけで、実際最近販売されているDTPシステムのほとんどには、写研製電算出力機へのデータ変換ソフトが用意されるようになった。そこで、次の例を設定しよう。●例4:1枚ものの商業印刷物(その3)
〔仮定:例2、3とほぼ同じ設定。発注者側は写研製データに変換が出来るDTPシステムで最終レイアウトを完成させており、写研製写植出力機での版下印刷を希望している〕一般の(汎用の)ワープロから写植データへのデータ変換ソフトは、レイアウト情報を移すにはあまり実用的でない。だが、特定のDTPシステムから特定の写植出力機(写研製など)への変換ソフトを作り込むなら十分実用的なものとして使える可能性がある。いったんDTPシステムで作ったデータを正確に(写研ならSKデータやスレーブデータに)変換して、それをフロッピーなどで写植出力機に持っていく。つまり図2-5のように、従来のシステムでは入力機、組版機、出力機がメーカー独自に一貫したシステムとなっていたものを、その途中で割り込むように、DTPシステムから写植出力機へのリンクが可能になってきたわけだ。
――― 図2-5 日本製電算写植機とDTPシステムのリンク ―――
こういうDTPシステムで作られた文書データなら、例3と同様に発注者が持ち込んだレイアウト済み文書を写研等の写植出力機に印刷できる。つまり組版過程のほとんどを発注者が内製化できる。しかも、手持ちのプリンターに普通紙で打ち出して校正をすればよいわけだから、校正のために高価な写植出力を何度も行わなくてよい。
ただ例3ほど流れが統一されているわけではない。
例3では、ポストスクリプトのような標準データ形式に対応しているフォントを入力時に確認できる。具体的な例で言えば、パソコンの画面上でモリサワのフォントの形や属性を確認しながら、どこのメーカー製のプリンターや写植出力機で印刷してもその確認したイメージをそのまま得ることが出来る。いわゆる「WYSIWYG」(What You See Is What You Get:見たままのものを手にする)がほぼ実現されている。
ところが、仮に例4で写研製写植機への出力を行う場合、DTPシステムと写研製写植出力機のリンクはできても、入力編集時に写研フォントを画面で確認できない。DTPシステム側は写研フォントとイメージの近い画面用フォントを使い、しかも文字幅データを正確にもってレイアウトしながらWYSIWYG的に操作させることが出来ても、本当にイメージの同じ出力が得られるとは限らない。特に商業印刷物の場合、こうした微妙な書体の違いや位置の違いで得られる出力イメージは結構大きな問題となる。入力から出力までを統一した表現形式で扱っていないことがどこまでもネックとなってくる。
なお、例2、3、4とも、ページ・レイアウト全体の電算処理最適化が出来なくても部分的にパソコンの能力を生かすことは可能だ。300dpi(ドット/インチ)以上の解像度を持つ高品質なプリンターで出力した結果で品質的に問題なしとするならば、イラストや図版だけでなく表計算ソフトで作成した表をそのまま版下として貼り込んで使うことが考えられる。
しかし、ここでも注意がいるのが原稿の修正である。発注者の段階で図版が完全版下として完成していてこそ内製化のメリットが出る。いったん出力を製版工程まで持ち込んでしまうと部分的な修正は利きにくい。発注者がそれまで組版や図表制作を印刷業者に任せていたのと同じ感覚でいると、後工程で修正が出て意外なトラブルを引き起こす可能性がある。内製化すなわち「発注者が自ら版下レイアウトや図表を作成する」とは、言い換えると「今まで印刷業者が行っていた成果物作成の責任を顧客に転嫁する」ことを意味する。仕事を請け負う側として、そのあたりをあらかじめ打ち合わせ、確認しておく必要があろう。
一般論で言えば、緊急の修正や追加、データの確認などが自由にできるように、印刷業者側も発注者と同じDTPシステムを装備しておくことが不可欠となるだろう。■完全レイアウトは必要か
例3や例4では、文字要素、図版イラスト、レイアウトに関して電子データとして受け渡しができることを見た。残ったのは写真、すなわち精密なイメージ・データをどう製版工程につなげるかである。
結論を言ってしまうと、こうした「トータルDTPシステム」は技術的に不可能ではない。だが、発注者がイメージ処理関連のシステムを完備するのは現実問題として不可能に近い。●例5:DTPによる雑誌の制作
〔仮定:発注者はパソコンまたは汎用のDTPシステムを利用し、レイアウトや図形を含んだ電子データを作り出すことが出来る。写真についてもイメージ・スキャナーで読み込んで製版に利用することを目指している〕1枚ものの商業印刷物や文字要素が中心の書籍に比べ、雑誌は写真、図版、文字が入り組んでいるため完全なDTPを実現するにはかなり高度なノウハウやシステムを必要とする。ここで想定する制作物は必ずしも雑誌と特定する必要はないかもしれないが、あえて雑誌を想定する。会社案内などカラー写真を含む数ページの印刷物作成においても、この例がある程度参考にできるだろう。
図2-6に精密なイメージ・データ含めて完全に電子化された「トータルDTPシステム」の例を図示した。編集者、制作者のレベルですべての原稿が電子化され、しかもレイアウトが確定される。このデータを印刷業者に受け渡すと、業者は電算写植機、製版機でフイルム出力する。図の点線で示したように、システムの整合性によってデータ変換が必要だろう。あとは印刷後工程に移る。場合によっては「ダクレクト刷版」といって、コンピュータ製版機から直接刷版まで済ませてしまうことも可能だ。技術的には、既にほぼここまで実現できていると言ってよい。――― 図2-6 例5(トータルDTP)のフローチャート例 ―――
ここで発注者側は、今まで述べた文字処理関係、図形処理関係の入力、編集機のほかに、画像処理関連で次のような設備が必要になる。
(1) 写真を高密度で読み取ることが出来るスキャナー。カラーを前提としたら、4色に分解したデータを得られるカラースキャナー
(2) スキャナーで読み取ったデータを編集レタッチ、集版するためのコンピュータ集版システム
(3) その他カラー・プリンターのような校正用出力機、画像入力を効率化するための準備機器、各種データをコンバートするインタフェースなど
結局、これは製版業者が装備しているシステムにほかならない。もちろん、多額の資金を投資してシステムを整備し、そのシステムを扱える担当者を育成すれば可能だが、フロッピー入稿やレイアウト文書入稿に比べるとかなり大掛かりになる。「写真をイメージ・スキャナーで読み込んでそれを製版に利用する」と言ってしまえば簡単だが、精密な画像読み取りが必要なイメージ・スキャナーおよびレタッチ等のシステム価格は数億円のレベルになってしまう。画像データの量も文字や図版データに比べれば膨大で、フロッピー・ディスクに換算すればそれこそ1画像で数千枚といったデータ量にもなる。これが、「フルDTP」が現実的でない理由である。
ただし、アップル・コンピュータのパソコンMacintosh(マック)を利用したカラー画像処理が急速に成長している。マック上のイメージ・レタッチング・ソフトPhotoshopやレイアウト・ソフトQuarkXPressでカラー・イメージやカラー・レイアウト文書を簡単に扱えるというだけでなく、サイテックス社(イスラエル)の製版システムとデータの連係ができることが入出力の幅を広げている。さらにライノタイプ・ヘルのクロマコム、アグファ・ゲバルト社や大日本スクリーン社などの各種システムがマックと連結できるようになった。高品質な製版までつなぐには品質の上で十分とはいえないが、“中レベル”の製版なら、コンピュータ・システムからみて射程距離にある。そもそも、画像処理でプロフェッショナルとしての品質が求められるケースと、一般企業のように「そこそこきれいな出力が出来ればよい」という場合とニーズのレベルはかなり幅がある。ユーザーの要求レベルとコスト・パフォーマンスが折り合う場合には、トータルDTPシステムの構築も現実味を帯びてくる。■編集方針の変更を迫られる可能性も
さて図2-6に戻ると、発注者が用意した印刷用データを元に印刷に入る前に、一応校正出力をとる必要性が考えられる。写植機、製版機から校正紙出力をして(または印刷機を回し色校正紙を出して)これを発注者に戻し確認を取る。問題はここで校正直しが出た(図の点線矢印)場合である。誰が直せばよいのだろうか。
もし、発注者のデータをほぼそのまま製版まで活用できていれば、発注者が元のデータに立ち返ってデータ修正を行うのが望ましい。たとえ出力の部分的な修正にとどまるとしても、部分的な修正貼り込みは、一般にはあまり簡単でない。また、業者が元のデータを大幅に修正してしまっている場合には、業者のシステムで修正する方がよいだろう。
そもそもDTPの意味は、編集者やデザイナーが自分の手元でほぼ最終的な校正確認が出来ることに大きな意味がある。確認後はもう修正が出来ないと考えて、完全版下、完全データの受け渡しをしてこそ、制作者の意図の正確な反映や納期の引きつけが可能になる。例1から例4で説明したことと全く同じく、校正をどの時点でどのように行うかを双方が確認しておくことがどうしても必要だ。それでも、雑誌などの場合、状況変化で直前の写真差し替えや本文修正が入りうる。その時はコンピュータを使っているかいないかに関わらず、「緊急事態として作り直す」と腹をくくる以外にないだろう。
作業工程をやや遡って、DTPシステムに目を向けてみる。
雑誌の場合、各ページのフォーマットがほぼ確定している書籍と異なり、コーナーごとページごとにレイアウトが変わってくる。そのレイアウトをWYSIWYGで処理しようとすると、画像データ処理を考慮しなくても、つまり写真についてはネガまたはポジで入稿し貼り込むことを想定しDTPシステムでは配置レイアウトさえはっきりさせておけばよいとしても、コンピュータにかなりのパフォーマンスが必要となる。一方、パンフレットのような商業印刷物と比べ文字要素が多いので、できるだけきれいな文字組版もできなければならない。例えばコンピュータ画面上で写研製電算写植機に準じた組版処理をシミュレーションしようとなると、これもやはりコンピュータに高性能が要求される。DTPシステムには、パソコンより高性能なワークステーションのシステムの方が向いていると思われる。
マックとPageMakerやQuarkXPress(米クォーク社)のようなレイアウト・ソフトでDTPシステムを構成し、それで雑誌作りをすることももちろん可能である。実例もいくつかある。だが、そのためにはフォントや組版などの点である程度割り切らざるをえないことになるだろう。その時は、雑誌や書籍作りのフィロソフィーと関係してくる。場合によっては、DTPシステムを入れることで逆に出版社や編集者の基本方針の変更を迫られることになろう。――― 図2-7 組版、写植、製版業者の守備範囲が縮まる ―――
■印刷に生きた情報を吹き込む
例1では文字要素だけが、例3、4では文字組版とレイアウト情報や図版が、そしてこの例では写真等が徐々に発注者が話で内製化され、全体として作業が川上にシフトしていった。ここで、最初に図2-2で描いた業務フローチャートに立ち返って、例4の場合にあてはめてみた(図2-7)。
図2-2と図2-7でモジュールの配置や名称はほとんど変更していない。変わったのは、発注者側が受け持つ作業が大幅に増え、印刷業者の仕事が極端に減ってしまったことだ。
フロッピー入稿に代表されるような顧客のわずかなコンピュータ化に端を発して、その後電子化に伴う問題点を解決しながら、さらにデータ電子化の利便性を追及してきた。その結果招いたのは、何と“印刷業者の自己否定”だった。印刷業者がやるべき仕事の大半がなくなってしまい、場合によっては単なる“プリンター屋”に成り下がる危険があるわけだ。
しかし、ここで大事なのは、編集者や制作者の電子印刷化が進んでも、印刷のノウハウをすべて身に付けているわけではないことだ。コンピュータ化したらそれなりの新たな印刷ノウハウも必要になる。また全工程を見渡した適切なシステム設計や運用技術提供、部分的なサービス提供も欠かせない。印刷業としての存在価値はそこにある。まさに、印刷業のソフト化でありサービス化である(図2-8)。――― 図2-8 電子化がもたらす印刷の変革概念図(3) ―――
“印刷とは情報伝達の手段である”ことを考えれば、版下作りや組版などが今後DTPにとって代わられたとしても、電子データをどう情報伝達に使えば良いのかをコンサルテーションすることのほうがより本質的な部分と言える。印刷業者が情報処理サービスの提供をし、その一環として紙媒体への印刷が存在するということだ。
●例6:DTPによる商用カタログ制作
〔仮定:DTPシステムを利用してページものの商品カタログを作成する。膨大な商品データがパソコンのデータベースに蓄積されているが、そのまま印刷物に使うには不完全なデータである。また、表組みの一部は表計算ソフトのフロッピーで渡されると想定〕カタログの場合、文字情報を読んでもらう書籍とは性格が異なり、商品なら商品のスペック(仕様)や価格情報を提供するところに意味がある。ものにもよるが、読みやすいように文章が配置されていることよりも、データが分かりやすい体裁で並び、しかも情報が正確であることが大事だ。商品のカラー写真が大事なカタログでは、色調を正確に出すための製版にも細心の注意を払わなければならない。
この例では、発注者がDTPシステムでレイアウトを組み、そこの商品情報をはめこむことを想定する。社員名簿や辞典、辞書の類を含め、こうしたデータベースをまとめた印刷物、出版物は世の中に数多く存在する(図2-9)。
もしその場限りの印刷が目的ならば、発注者側は紙に書かれている情報でも何でもよいから印刷会社に渡してしまい、何百ページにも渡る情報を印刷会社が苦労して入力し組版すればよいことになる。だが、これでは次に作り直すときにまた一からデータを整理し、編集し、印刷するはめになる。その度に印刷会社が大変な作業をしなければならないのはもちろんだが、発注者にとっても作業の効率化、短納期化、ミスの低減を図ることは期待できない。どうせならばコンピュータで文字情報だけでもデータベース化してしまい、必要に応じてデータのメンテナンスを行い、最小限の編集、校正作業で印刷物が完成するように考え方をあらためた方がずっと賢いやり方と言えよう。
これが「電子データをどう情報伝達に使えば良いのかをコンサルテーションする」例である。大事なのは、「紙への印刷が目的」との意識を転換して、もっと本質的な目的はデータベース情報の整備であり、その結果としてカタログのような「印刷物も制作する」という方針を持つことである。データベースを印刷以外の業務にも十分活用できる可能性がある。むりやり既存の統合データベースに連動させる必要はないかも知れないが、コンピュータと電子印刷が相乗効果を生むことで新たな展開が開ける。
データベースから電算写植出力機などへデータを関係付けるためには、次の二つのハードルを乗り越える必要がある。
(1) 初期データを誰がコンピュータに入力するか。誰がデータベースをメンテナンスするか
(2) コンピュータのデータを写植機にどのようにコンバート(変換)すればよいか
(1)については、発注者側がもともと持っているデータベースを利用するなら入力に関しては問題ない。メンテナンスについても、データの追加、更新が的確に行われる体制が出来ているならそれでオーケーだ。ただし、これまで紙でデータ管理していたとしたら、膨大なデータでもとにかく最初に入力する必要がある。例えば印刷が目的だと言って電子組版システムに文字属性やレイアウト情報を混ぜながら入力していくのではなく、情報処理に生かすことを考えてまずパソコンなどのデータベース・システムを構築していくことが期待される。
(2)については、現実のところデータベースの構造と印刷フォーマットにより変換すべき手順が異なるため、単に市販のデータ変換ソフトを使えばすむというわけにはいかない。ケースごとにほとんど独自のデータ変換作業が必要となる。
一般に、(1)、(2)すべてを発注者が自力でクリアできるわけではない。むしろ、電算写植機とデータベースのリンクをどうとれば効果的なのか、検索用インデックスをどう索引づくりに利用するかなど、印刷業者の力が必要とされる場面が数多くある。そこに、印刷業者の情報処理サービス業として欠くことの出来ない使命が生まれてくるわけだ。一般のソフトハウスやシステムハウスと呼ばれるコンピュータ屋では印刷実務や印刷システムを必ずしも理解していないため、的確なデータベース構築指導や変換ソフト開発を出来るとは限らない。そもそも電算写植機を持っていて実際に写植出力の結果を提供できるソフトハウスなどほとんどないだろう。しかし、(仮に高価な出力機は持っていないとしても)印刷に関わる難しい問題を理解している印刷業者なら、ちょっとしたプログラミング・ノウハウとデータベースの知識を身に付けるだけで、顧客ニーズに対応したサービスを提供できる可能性がある。
大掛かりなデータベースの印刷でなく、例えば「表計算ソフトの1-2-3(ロータス社)で作成したデータがフロッピー・ディスクに入っているが、これを表組みデータとして利用したい」といったニーズに対応できるだけでも、発注者からの信頼を得ることが出来るだろう。そのためには、一般的なコンピュータの知識、標準的なデータ形式や市販パソコン・ソフトの概要を理解しておく必要がある。
ちなみに、パソコン表計算ソフトからのデータ変換手法は何通りもあるが、一例を挙げると以下のようになる。
まず、表計算ソフトからMS-DOS標準テキスト・ファイルでデータベースを保存する。「カンマ区切り」(あるいは「タブ区切り」)形式と呼ばれる標準データ形式が汎用性があって望ましい。このデータベースを、高機能な文書エディター(editor:編集プログラム)で読み込む。そして写植出力のフォーマットに合うよう文字の置き換え、罫線コード等の挿入、不要文字の消去など行う。エディターに備わっているマクロ機能などを使えば、この変換作業は一括処理で済む。これで、表組データが自動的に出来上がる。最後にデータ変換ソフトで電算写植機で読めるデータ形式に変換すればよい。この程度なら、特に難しいコンピュータ・プログラミングを修得している必要もないので、ある程度情報処理に詳しい人材を育てれば、一般の印刷業者でも十分可能と言えるだろう。
もう一言触れると、表データ中に罫線コードや組版ファンクション・コードを埋め込んでしまうとそこでデータが「印刷専用」になってしまう。可能ならば、データの中身とは別に表枠を作図しておき、表内にデータを貼り込むプログラムを組んでおく方がよい。データベースを元データのままで扱えるようにしておくことで印刷以外の情報処理につなげられるし、元のデータベースに変更があった時に無理なく印刷にも反映できる。