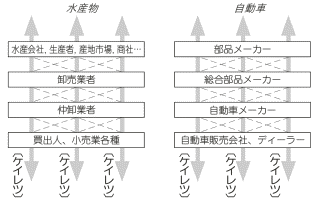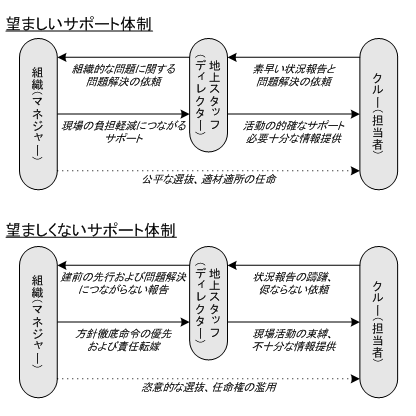日本の流通システムは、かねてから閉鎖的と外部から指摘されてきました。しかし少なくとも生鮮品の流通に関しては、ローカルな制度が将来的にも高い価値を持ち続けるであろうことを、この本が示唆しているように思えます。

「築地」(挿絵)
テオドル・ベスター氏の著書についての話、「築地」、「築地」その2の続きです。
■意図しない“非関税障壁”
またしても築地市場とは少し離れた話ですが、一昔前(1995年くらいまで)の日本のパソコン市場は、今と違って世界標準規格から逸脱した構造の商品が市場のほとんどを占めていました。なかでもNEC「PC-9800シリーズ」がその最大手で、国内でパソコンをまともな業務に使うには「98」以外の選択肢はなかったようなものでした。一方、日本を除くほぼすべての国では基本的に「IBM互換」タイプのパソコンが使われていました(さらに余談ですが、現在は携帯電話がこの状態―いわゆる「ガラパゴス化」―にあるようですね)。
その時代、海外(欧米やアジア)のパソコン業界関係者と話をしたときにときどき出てきた質問がありました。
「なぜ日本は世界標準に従わない? わざわざ独自の仕様を守り外国企業を締め出している。非関税障壁ではないか」
質問というより糾弾に近いニュアンスを含んでいたことを覚えています。そしてこの言葉の裏には、パソコンだけでなく、日本市場全般の閉鎖性に対する不信感があったととらえています。
日本のパソコン利用者という立場からすると、「わざと独自仕様を守る」意識など誰にもなく、ましてや国全体が一つの意思を持って外資の侵入を防いでいたというものでは決してありません。要因を列挙すれば、次のようになるでしょうか。
(1) IBM互換機の規格だけでは日本語処理機能(2バイト文字の扱いなど)が十分でなく、どうしても小手先の対応ではない、高いレベルでローカライズをする必要性があった
(2) メーカーも流通業者も、日本市場の特殊性やローカル色のある取引形態に対応することが商売上なにより有利だった
(3) 日本の主な電機メーカーは、(あえて海外の規格を持ってこなくても)独自規格と独自の商品を作り出すだけの実力があった
(4) ある時点で「98」がソフト資産を十分に蓄えてしまい、乗換えが難しくなった
その後パソコンの性能向上その他さまざまな条件が変化し、今は状況が完全に転換しました。「98」は姿を消しました。「IBM互換」という言葉さえ消滅したように、現在日本を含めた世界全域で使われているパソコンは、ほぼ共通したデファクト・スタンダードに沿った構造になっています(Macintoshは違うけど)。
そのほかさまざまな業種で、過去にあった非関税障壁はとりはらわれるか、少なくとも低いものとなってきました。金融、会計、その他の分野にまたがり閉鎖性が薄まってきたのが、1990年代後半から2000年代前半だったと認識しています。
■腐った魚は買い叩く!
この観点だけから見れば、築地のような生鮮品の流通機構は、外部からなかなか食い込めない閉鎖性を今でも持っていて、いずれなくなるべき対象といえなくありません。もし将来、卸売市場の制度が大きく変わり、強い外資ファンドが「築地」を乗っ取ろうとでもしたら、いったいどんな影響があるでしょう。
「未だに日本の流通システムは“変革すべき対象”なのだ」
「官営で市場を守るなど時代遅れだ」
「中にいる卸売業者も中卸業者も、自ら変わろうとする意思が弱い」
「旧来のやり方にこだわり、市場移転を何が何でも反対する勢力がいる」
「そんな腐った流通システムを買い叩く! 買い叩く! 買い叩く! 」(ドラマ「ハゲタカ」風……)
買い叩くのは「腐った魚」だけにしてください、とか言いたくなるかもしれません(笑)。
本書の著者も、築地を研究対象とした背景に次のような問題意識があったようです(少し意訳して表現)。
→政府の規制と政治的圧力が日本の独特な流通システムの原因と見る一派は、日本は故意に閉鎖経済を行っていると見ている
→日本経済は、その社会的・文化的生活の特性をなお保持しており、これは一夜にして消えるとは思われないと(その一派は)見ている
→本当なのか、その解を探りたい
■外部の変化が築地を消し去ることはない
日本の卸売市場システムの閉鎖性についても、かつてのパソコン市場と同様、「独自仕様を守る」という意識が先に立って出来上がったわけではないはずです。著者の問題意識から、本書のあちこちにその答が書かれていることを実感します(以下、パソコンの話の(1)~(4)と対応させて表現)。
(1′) 魚の食べ方や嗜好性には日本文化独自のこだわりがあるので、どうしても小手先の対応ではない、高いレベルで日本の食生活に対応した加工処理をする必要がある
…本書第4章「生ものと火を通したものと」などから納得できる。
(2′) 生産者も卸売業者も中卸業者も小売業者も、相互の特殊な取引ニーズに対応できることが商売上なによりも有利である
…縦横に編み上げられた「関係性」が強力すぎるということか
(3′) 築地の卸売人たちは、(あえて海外の取引システムを持ってこなくても)きめ細かい取引システムを自ら生み出せる資質があった
…著者は「築地は高度に秩序のとれた場所」と評している
(4′) ある時点で卸売市場のシステムが確立してしまい、乗換えが難しくなった
…これについては、市場法など中央集権的な政策が一役買っている
結論的に、築地魚河岸は一見伏魔殿のようでいても、
・開発途上国のバザールのようなものと異なるシステム性がある
・マグドナルドのようなシステムとも全く異質のシステムである
・決して非合理的というわけではなく、むしろ高度なものである
・だから、外部の変化が築地の社会的構造をきれいさっぱり消し去ることはないだろう
と著者は表現しています。
■築地移転問題にも一矢
他のブログや雑誌にある本書の書評に「それみろ、外国人だって築地の優秀さに言及している。だから築地の豊洲移転に絶対反対すべきなのだ」といった方向で感想が書かれているものをいくつか目にしました。本書に書かれている築地文化の“価値”が、移転反対派を勇気付けていると推測されます。
しかし、本書が築地移転反対論者の“バイブル”になるとも思えません。その理由は次のような点にあります。
・本書には“築地”の「功」は見事に描かれていても「罪」についてはわずかしか触れていない。「功」の部分だけを過大評価できない(前回記事の末尾参照)
・“築地”を成立させている文化的背景が堅固なものならば、それは豊洲に移転しても確実に受け継がれるはず(外部の変化が築地を消し去ることはない)
・素晴らしい仕組みがあったとしても、時には時代の変化に沿うように積極的に壊さなければ次に進めなくなるものもある(パソコン「98」のように…)
市場が移転しても移転しなくても、長期的に見るとどちらでもたいした違いではない気もします。
とりあえず、テオドル・ベスター著「築地」の書評(+α)はこれでおしまい。